色によって紫外線の吸収波長が違うのはなぜ?
2000年7月13日に 女性の方からご質問を頂きました.。
色によって、紫外線の吸収量が違うと聞いたのですが、本当ですか?
色によって紫外線の吸収量が違うということですが、「科学のつまみ食い」のホームページの「色によって洗濯物の乾き方が違いますか?」を参考にするとわかると思います。
ここでは、簡単に説明します。色の違いは波長で表されますが、紫外線自体は青や紫よりもと波長の短い目に見えない光です。ですから、実際にはわれわれの目に見える色で判断することは困難です。「科学のつまみ食い」のホームページの「色によって洗濯物の乾き方が違いますか?」では赤外線に触れていますがこれを紫外線に置き換えても同じです。従って、目に見える色で紫外線の吸収量が多いか少ないかは一概に言えません。
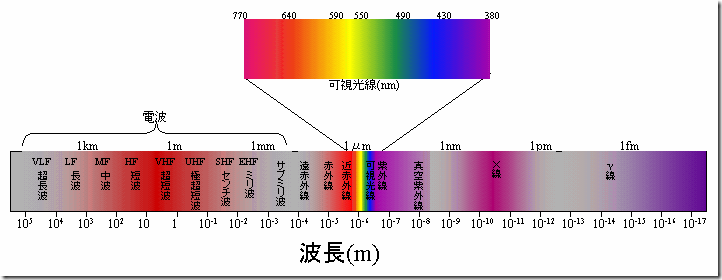
ただ、赤外線は赤い色の近く、紫外線は紫色の近くの光ですから、赤い色は赤外線を吸収し難く、紫の色は紫外線を吸収しにくいかもしれません。しかし、それよりも色の濃さのほうが吸収量に大きな影響を与えるでしょう。白い色は紫外線に限らずすべての色を反射しやすく、黒い色はすべての色を吸収しやすいといえるでしょう。
さて、赤い服は赤い色を反射しますが、もともとの光は何処からきたものでしょう?
戸外なら太陽の光でしょうし、屋内なら蛍光灯や電球の光ですね。ここでは、太陽の光で話をします。
プリズムは知ってますか?
プリズムは光の色を分けることができます。太陽光をプリズムに通すと、「色によって洗濯物の乾き方が違いますか?」の時に書いたように、虹の色の順番と同じく、赤(800nm)、橙、黄、緑、青、紫(400nm)という具合に下の図のように光が分かれます。ちなみに虹は空気中の水蒸気がプリズムの役目をしているのです(形は三角ではないですが…)
